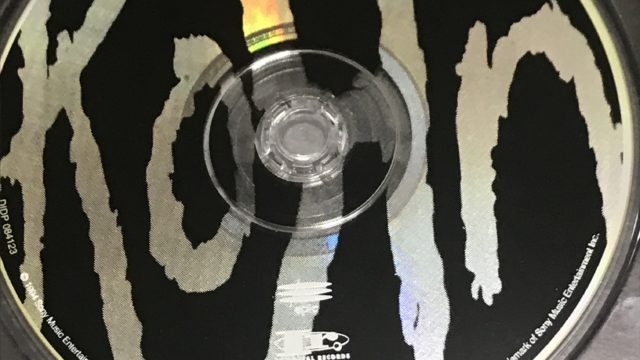ポップさはあるけれど、明らかなロックアルバム 『Sam’s Town』THE KILLERS
2000年代序盤というと、古めのロックのサウンドを鳴らすバンドが多く世に出た、ロックンロール・リバイバルの流行が印象的です。特に、ガレージ・ロック系のバンドの活躍を個人的にはよく覚えています。ストロークスやホワイト・ストライプを始めて聴いた時には、古い音を鳴らしているのに、新しいバンドが生まれたと思いました。元々、そんなに昔(70年代とか)のロックを聴いてなかったせいもありますが。
知らなかったんですけど、同時期にポストパンク・リバイバルとかニューウェイブ・リバイバルと呼ばれる現象もあったんですね。ガレージ系サウンドとは異なり、シンセサイザーを多用したりダンサンブルな楽曲を主とする音楽性で、80年代のニューウェーブ風のサウンドを発展させた、ポップ色が強いロックといった感じです。
今回取り上げるTHE KILLERSも、デビュー作『Hot Fuss』(2004年)の時期はそんな印象のバンドでした。煌びやかなシンセイサイザーのサウンドとポップでキャッチーなメロディ。「Mr. Brightside」や「Somebody Told Me」といったヒットシングルも印象的な、デビュー作としては出来すぎな名曲揃いのアルバムです。
アメリカン・ロックを強く意識したアルバム
ただ、2ndアルバム『Sam’s Town』(2006年)の、全編を通して伝わる骨太感の方が個人的には好みですかね。とは言え、1stと同じようにシンセサイザーも多く使われていますし、中心人物のブランドン・フラワーズ(Vo&Key)が生み出すポップでキャッチーなメロディも健在です。ハードロックバンドと比べると、そこまで男臭さや骨太な印象は受けないかもしれません。でも、このアルバムからは “ロック” という色をすごく濃く感じるんですよね。
タイトルトラックでもあり、アルバム冒頭を飾る「Sam’s Town」の壮大なオープニングがそれを物語っています。いかにも1曲目を飾るに相応しいオープニング・ナンバーといった曲調で、特にロニー・ヴァヌッチィ(Dr)のドラムさばきに高揚感が高まります。ブランドンのコーラスも内なる叫びではなく、外の世界に向けて歌い上げているように聴こえます。キャッチーでセンチメンタルなメロディなのに、ロックを感じますねえ。
そしてこのアルバムと言えば、何といっても「When You Were Young」ですね。
「Sam’s Town」の次に「Enterlude」という小曲を挟んだ曲ですが、この曲のダイナミズムと切なさの融合っぷりといったら、もう最高!デイヴィド・キューニング(Gt)のギターが非常にカッコいい曲で、明らかに前作にはなかったタイプの楽曲です。一旦、静かになってから後半に畳みかける展開がもう堪らないんですよね。
このアルバムを作るにあたって、ブルース・スプリングスティーンの影響があったということですが、納得のスタジアムロックナンバーです。
※PVの前半の芝居パートが長いため途中からの再生です。
「Bling(Confessions Of A King)」はイントロからしばらくはダークな曲調ですが、その分、後半には希望の光を見出すようなブランドンのヴォーカルが映えます。リズム隊のタイトな演奏とシャープなギターも決まってますね。
「For Reasons Unknown」は彼らのポップさが強調された曲。それにしてもブランドンのヴォーカルの表現力に感心します。曲調はポップなのに、彼のヴォーカルからはセンチメンタルがひしひしと伝わってきますから。
もしかしたら日本に限っては、彼らのPVの中で最も有名かもしれない「Read My Mind」。なぜならば日本で撮影された上に、あの有名キャラクターのガチャピンが出演しています。
PVの内容はメンバーが日本観光(?)しているだけで、ガチャピン出演シーン以外は特に見どころのないものですが、曲そのものは秀逸。ブランドンのヴォーカルがいつまでも耳に残る素晴らしい楽曲です。
ブランドンの叔父さんをモデルにしたという「Uncle Jonny」は暗い雰囲気の曲です。延々と続く硬質なギターリフに絡みつく、マーク・ストーマー(Ba)の起伏に富んだベースラインが印象的です。
キラーズらしいキラキラ感のある「Bones」はサックスなどのホーン・セクションも加わり、ゴージャス感も味わえます。如何せん、メンバーが骸骨に変わるという演出のPVがめちゃくちゃダサいのが残念ではあります。
「My List」はパワフルなヴォーカルのラブソング。前半パートはおとなしいのですが、途中から力強いドラムと共に、エネルギッシュな演奏へと変化します。この曲でもブランドンのヴォーカリストとしての表現力を堪能できます。
「The River Is Wild」は大仰な感じはしますが、ドラマチックで壮大な曲です。この曲もブルース・スプリングスティーンに繋がるアメリカン・ロックらしさがありますね。
厳密には「Exitlude」という小曲が最後の曲ですが、ひとつ前の「Why Do I Keep Counting?」は今作の大団円に相応しいナンバーでしょう。そこはかとなく感じるクイーンっぽさ。ヴォーカルだけでなく、コーラスやハーモニーもよく練られています。「The River Is Wild」と比べると落ち着いた曲ですが、この曲にも壮大さを感じることができます。
彼らの音楽の良さって、結局はメロディの良さにあるんだと思います。僕はあまりシンセサイザーを多用するロックはあまり聴かないんですが、彼らに関しては シンセがあろうがなかろうが関係なく聴き入ってしまいますね。それはひとえに楽曲の良さ、というよりも “歌” が良いんではないかと。ハードなロックと比べると、軽く聴こえる部分もあるんですけど、ポップではなくロックとしての良さが満ち溢れたアルバムには違いありません。